スタッフブログ
宅建勉強12月28日(火)
問32
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
- AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
- AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
- AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。
解説
- “AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。”[正しい]。手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手するまでにしなければなりません(宅建業法39条2項)。本肢では、買主Bが既に契約の履行に着手しているので、売主Aは倍額を現実に提供しても手付解除をすることはできません。
- “AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。”誤り。クーリング・オフによる契約解除があった場合、売主である宅地建物取引業者は買受けの申込みや契約締結の際に受領した手付金等を速やかに返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。この規定に反する特約で買主に不利な特約は無効となります(宅建業法37条の2第4項)。
クーリング・オフを実行した際に手付金が戻ってこない特約は、明らかに買主に不利なので無効となります。 - “AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。”誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主とする割賦販売契約において、買主からの割賦金支払いが行われない場合には、30日以上の期間を定めて書面で支払いを催告した後でなければ、そのことを理由として契約解除・残額の支払いを請求することはできません。本肢は「直ちに…契約を解除することができる」としているので違反行為となります(宅建業法42条)。
- “AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。”誤り。未完成物件の場合は、受領しようとする手付金等の額が(受領済の額を含めて)代金の5%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります。
 本肢の建物の代金は5,000万円ですから「5,000万円×5%=250万円」以下ならば保全措置不要で受領できます。Bから受領しようとしている手付金は200万円なので保全措置を講じる必要はありません。
本肢の建物の代金は5,000万円ですから「5,000万円×5%=250万円」以下ならば保全措置不要で受領できます。Bから受領しようとしている手付金は200万円なので保全措置を講じる必要はありません。
したがって正しい記述は[1]です。
宅建勉強12月27日(月)
問29
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
- Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
- Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
- Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
- “Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。”正しい。専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡す必要があります(宅建業法34条の2第6項)。
- “Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。”正しい。媒介契約書には、国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かを記載する必要があります(施行規則15条の9第4号)。これは、媒介契約の形態(一般・専任・専属専任)を問いません。標準媒介契約約款とは、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項のことです。

- “Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。”誤り。専任媒介契約の有効期間について自動更新を約定することは許されていません(解釈運用の考え方-第34条の2関係)。依頼者の同意があった場合でもダメです。専任媒介契約の最長期間は3カ月ですので、継続が必要な場合は依頼者からの申出により改めて契約を更新する必要があります(宅建業法34条の2第4項)。
- “Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。”正しい。専任媒介契約では依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告する義務があります。報告頻度は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上です(宅建業法34条の2第9項)。
したがって正しいものは「三つ」です。
日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(26)
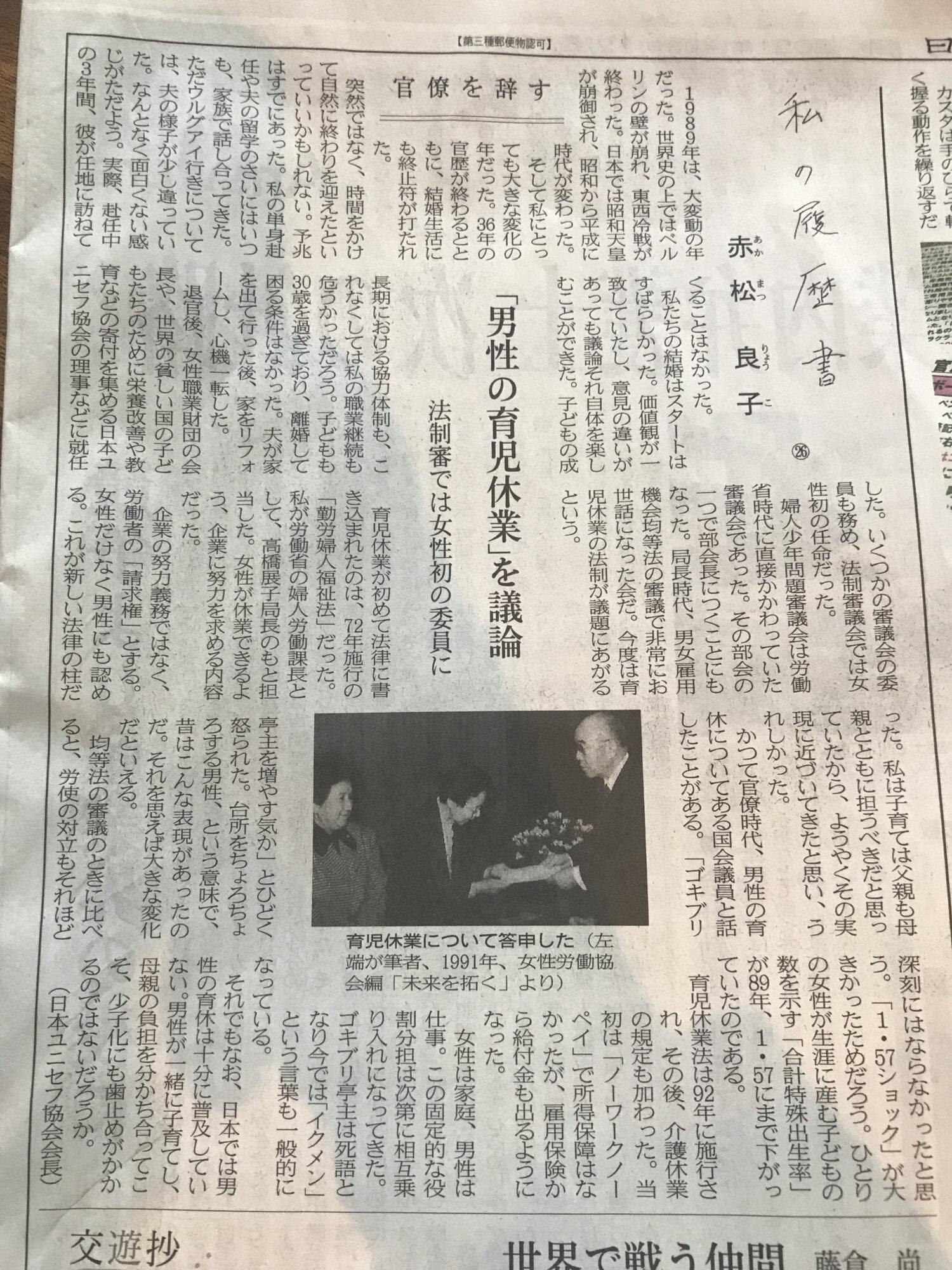
官僚を辞す
「男性の育児休業」を議論 法制審では女性初の委員に
1989年は、大変動の年だった。世界史の上ではベルリンの壁が崩れ、東西冷戦が終わった。日本では昭和天皇が崩御され、昭和から平成に時代が変わった。
そして私にとっても大きな変化の年だった。36年の官歴が終わるとともに、結婚生活にも終止符が打たれた。
突然ではなく、時間をかけて自然に終わりを迎えたといっていいかもしれない。予兆はすでにあった。
ノーワーク・ノーペイ
男性の育児休業に関して、以前では働かないのであれば支払われるものもない、ということが当たり前、女性は家庭。男性は仕事という固定概念を少しずつ取り入れられる世の中になっていることが記載されておりました。
きちんと働き、相手に・周囲に・会社に・社会に貢献して、働くからこそ、こういった考えがあると私は思います、色々な考えの方はいると思いますが、働き、周囲からの声が自身の評価ということを心に留め仕事をしいきます。
お客様に対して、自分は頑張った・説明した・喜んでもらえたと自分で思ったことは大切ではなく、お客様がどう感じてどの様な判断をしていただいたかが結果と思いお手伝いさせて頂きます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 赤松良子 を読んで(25)

ウルグアイ大使
裏方でGATT支える スペイン語必死で学び講演も
1985年秋。労働省の次官から大使赴任の打診があった。男女雇用機会均等法が成立し、翌年の施行に向け最後の仕上げに入っていたときだった。
外交官としてはすでに国連公使の経験がある。打診自体は意外ではなかった。労働省の先輩、高橋展子さんが80年に初の女性大使(デンマーク)となり、「自分に続く大使が現れないと、女性は困るといわれているみたいで嫌だ」とやきもきしているのも知っていた。
新しいことを始める、新しい考え方を取り入れる、自分とは違う意見を取り入れる、今の自分を変えることはとても難しいことと私は考えております。赤松氏は何歳になっても、新しいことに挑戦するのは楽しい。語学・ゴルフ・タンゴ。とおっしゃっておりました。新しいことを始め、新しいことを取り入れることを楽しいと思える人になりたいと思いました。
私は会社から営業ツールを与えられ、使わされているという立ち位置で仕事をしております。自ら活用して良い提案をお客様に届ける、誰に対して仕事をしているのか。お客様により良い提案ができる様に『自ら』を意識します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建ブログ12月25日(土)
山田さん、解答有難う御座います。
【令和2年問4 賃貸借契約】
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
賃貸借契約終了時の退去時の精算について分かっているか。
原状回復義務=契約前の状態に戻す義務
1.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。(×)
=通常の使用及び収益によって生じた損耗これを実務上、通常損耗と言います。要するに普通に使って劣化したものについては、原状回復義務はない。
2.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。(×)
=賃借人に帰責事由がなければ原状回復義務はない。
3.賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。(〇)
=敷金は賃借物の返還までに生じた一切の債権を担保するために預かっているもの。あくまで建物を引き渡すことが先決。
4.賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。(×)
=家賃滞納をしている入居者が大家に電話して、今月厳しいので家賃を敷金で充当してくださいということ。賃借人から敷金を充当してとは言えない。
宅建ブログ12月24日(金)
山田さん、解答有難う御座います。
【令和2年問4 賃貸借契約】
建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
賃貸借契約終了時の退去時の精算について分かっているか。
原状回復義務=契約前の状態に戻す義務
1.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。(×)
=通常の使用及び収益によって生じた損耗これを実務上、通常損耗と言います。要するに普通に使って劣化したものについては、原状回復義務はない。
2.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。(×)
=賃借人に帰責事由がなければ原状回復義務はない。
3.賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。(〇)
=敷金は賃借物の返還までに生じた一切の債権を担保するために預かっているもの。あくまで建物を引き渡すことが先決。
4.賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。(×)
=家賃滞納をしている入居者が大家に電話して、今月厳しいので家賃を敷金で充当してくださいということ。賃借人から敷金を充当してとは言えない。
宅建ブログ12月23日(金)
山田さん、解答有難う御座います。
【民法 令和2年問1】
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。(〇)
=共有物の分割によって公道に通じない土地はできなかったらAは閉じ込められてしまう・・・
2 Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。(×)
=歩いて通っても良いが車ではだめ。車で通れる道幅があれば通ってもOK。
自動車による通行権は認められることもある。
3 Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。(×)
=賃貸借問題。甲土地の賃借権は従たるものとして移転するか。Bが乙土地を賃借するためにはAから買うか、転貸してもらわないといけない。必要なのは賃貸人である乙土地の所有者の承諾です。
4 Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。(×)
=ちなみにこれが通行地役権だった場合、民法289条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは地役権はこれによって消滅する。
別問題
Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合、Cが甲土地にはBの通行地役権の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得した時は、Bの通行地役権は消滅する。(〇)
=ちなみに、時効取得したものが地役権の存在を認めていた場合には地役権は消滅せず、地役権付の所有権を時効取得することになります。
宅建ブログ12月22日(水)
山田さん、回答ありがとうございます。
【相続:限定承認について】
ステップ1:家庭裁判所に申し立てる。
「相続開始を知った日から3カ月以内」
相続人全員で故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申し立てを行います。
全員一致しないとダメ。
ステップ2:除斥広告を行う。
除斥広告とは債権者や受遺者に対して「権利がある場合は申し出てください。」と官報を通じて知らせることです。
申出の期間は2か月以上に設定する必要があります。
ステップ3:弁済する
まずは、先取特権とか抵当権など優先権を持っている権利者に優先的に弁済する。相続財産で全債務を完済できない場合については「債務額の割合」に応じて弁済します。
ステップ4:受遺者に弁済する
債権者に弁済して余剰がある場合は受遺者に弁済します。
受遺者とは、遺言書によって遺産を受け取る人のことです。
ステップ5:相続人が受け取る
すべての債務を弁済し終えても相続財産が残っている場合は、限定承認をした相続人が残った財産を受け取ります。
平成29年 問6
Aが死亡し、相続人がBとCの 2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から 3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、 Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。(×)
=BとCが共同して行わないといけない。Bが限定承認を選んだからと言って、Cも限定承認とは限らない。
平成14年 問12
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。(〇)
宅建勉強12月26日(日)
住宅比較の吉田です。
問29
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
- Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
- Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
- Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
解説
- “Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。”正しい。専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡す必要があります(宅建業法34条の2第6項)。
- “Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。”正しい。媒介契約書には、国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かを記載する必要があります(施行規則15条の9第4号)。これは、媒介契約の形態(一般・専任・専属専任)を問いません。標準媒介契約約款とは、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項のことです。

- “Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。”誤り。専任媒介契約の有効期間について自動更新を約定することは許されていません(解釈運用の考え方-第34条の2関係)。依頼者の同意があった場合でもダメです。専任媒介契約の最長期間は3カ月ですので、継続が必要な場合は依頼者からの申出により改めて契約を更新する必要があります(宅建業法34条の2第4項)。
- “Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。”正しい。専任媒介契約では依頼者に対して定期的に業務の処理状況を報告する義務があります。報告頻度は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上です(宅建業法34条の2第9項)。
したがって正しいものは「三つ」です。