スタッフブログ
宅建勉強1月18日(火)
問12
AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
- AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
- 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
- AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
- Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
解説
- “AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。”誤り。有効な定期建物賃貸借契約とするためには、公正証書による等書面によって契約するだけでは足りず、賃貸人から賃借人に対して、契約の更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要があります(借地借家法38条1項借地借家法38条2項)。なお、この書面は契約書とは別個の書面でなければなりません(最判平24.9.13)。
- “甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。”誤り。本肢のように、居住の用に供する建物である場合に定期建物賃貸借契約を締結できないといった規定はありません。居住用建物でも更新がない旨を定めることができます。
- “AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。”誤り。期間の定めのある建物賃貸借では、賃貸人から賃借人に対して、期間満了の1年前から半年前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。本肢は「3月前まで」としているので誤りです。
- “Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。”[正しい]。建物の転貸借が期間満了や解約申入れにより終了する場合、通知なくして転借人に終了を対抗することはできません(借地借家法34条1項)。逆に捉えると債務不履行による契約解除の場合は、通知なくして転借人に対抗できるということです。
したがって正しい記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(16)

米国留学
GM直営大学で猛勉強 いすゞ4人組でゴルフも腕磨く
世界の自動車業界の頂点に君臨していた米ゼネラル・モーターズ(GM)には数々のレガシー(遺産)があったが、そのひとつに直営の工科大学があった。名称はゼネラル・モーターズ・インスティテュート・オブ・テクノロジー。米国内では「GMI」という略称で知られていた。
1919年にGM創業の地ミシガン州フリントの工業組合が出資する自動車商業学校として発足。26年にGMが経営権を取得し、32年にGMIに改称した。
どれだけ学び、どれだけ資格を得ているか。企業で出世できる方・するための最低条件はどれだけ学び、どれだけ資格を有しているかが判断の基準となっていることを知りました。企業に勤めてからも自身でどれだけ勉強の場を作り参加し、どれだけのことを得てくるのかが大切かを知りました。
成長のわかりやすい指針が資格、常に何の資格をいつまでに取るかを決めてそのための勉強の時間を作っていこうと思います。
お客様に対して、安心や信頼を頂くための一つとして正しい知識や情報をどれだけお伝えしお役に立てるかが関わってくると思いました。
知識を増やし、安心いただける提案をしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月17日(月)
問11
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。
- 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
- 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
- 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
解説
- “賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース①は期間の定めのない契約になり、ケース②では期間は15年となる。”誤り。本肢の場合、資材置き場であり建物の所有を目的としないため借地借家法は適用されず、民法の規定が適用されます。民法では賃貸借契約の最長を50年としているため、ケース①は50年、ケース②は15年となります(民法604条)。
- “賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。”誤り。本肢の場合、建物の所有を目的とするので借地借家法が適用されます。普通借地権については契約方法は定められていませんが、存続期間の最短が30年です(借地借家法3条)。よって、ケース①は50年、ケース②は30年となります。
- “賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。”[正しい]。居住用建物については事業用定期借地権等を設定できません。一般定期借地権の存続期間は50年以上なので、ケース①は50年、ケース②は50年未満なので更新のない定めは無効となり、普通借地権の最短期間である30年となります(借地借家法22条)。
- “賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。”誤り。
[ケース①]
事業用定期借地権等は公正証書で契約しなければなりませんが、存続期間50年なので一般定期借地権として契約することも可能です。この場合、公正証書に限らず書面であれば問題ありません。
[ケース②]
存続期間15年の定期借地権を設定できるのは事業用定期借地権等だけです。本肢は工場の所有を目的としている(居住用ではない)ので、公正証書で契約すれば存続期間15年で更新がない賃貸借契約とすることができます。
なお、10年以上30年未満の事業用定期借地権では「契約更新がない」「建物買取請求権がない」「築造により存続期間延長がない」旨の特約をしなくても上記の効果が生じます(借地借家法23条2項)。よって必ずしも「契約の更新がないことを公正証書で定め」ることは求められませんが、もし定めたとしても無効になるわけではありません。
したがって正しい記述は[3]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(15)

技術者修業
車が大好き 金型で成果 高価な機械導入、工期大幅短縮
いすゞ自動車の新人時代に話は戻る。配属された生産技術部門は予算不足で開店休業状態だったが、おかげで仕事に慣れる時間は十分にあった。大いに勉強になったのは同業他社との交流。当時は機密漏洩だなんだと神経質になることはなく、同じ生産技術に携わる技術者同士が会社の枠を越え自由に話ができた。現場見学の機会もあり「こんな風にやっているんですか」と感心したり、またはさせたり。おおらかな時代だった。
知識の共有、切磋琢磨
今では情報漏洩など問題がありますが以前は関係なく知識を高めあうことができたことを知りました。
今も自分だけの成果を考えてしまうことがあるが共に結果を出すことでの成果を考え必要があると思いました。
お客様がより喜んでいただくためには私だけでなく多くの方の協力を得てサポートすることでより喜んでいただけるようにします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月16日(日)
問10
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 600万円
- 1,000万円
- 1,440万円
- 1,600万円
解説
抵当権は、一般の私債権よりも債権順位が上になります。また抵当権者の中では順位が若い方が優先して弁済を受けられるので、本問のケースでは、譲渡も放棄もなければ原則として以下のように配当されます。
- B … 2,000万円
- C … 2,400万円
- D … 1,600万円
BからDに抵当権の順位が譲渡された場合、BD間ではDが優先して配当を受けます。BとDの配当の合計は「2,000万円+1,600万円=3,600万円」ですから、Dにはこの3,600万円が優先して配当され、残った額がBに配当されます。Dの債権額は3,000万円ですから、Dに3,000万円が配当され、Bの受ける配当は600万円になります。
- B … 600万円
- C … 2,400万円
- D … 3,000万円
したがってBの受ける配当額は600万円です。
なお、BからDに抵当権の順位が放棄された場合、BDの配当の合計はBD間で債権額の割合に応じて配分されることになります。BとDの配当の合計は「2,000万円+1,600万円=3,600万円」、債権額は B:2,000万円、D:3,000万円ですから、BDの配当額の合計3,600万円は「B:D=2:3」で配分されることになります。
- B … 1,440万円
- C … 2,400万円
- D … 2,160万円
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(14)

石油危機
父「超短期で新製品」号令 創業期の難局 海外技術で打開
いすゞ自動車入社から半年後の1973年10月、第4次中東戦争が起こった。第1次オイルショックの引き金となり、原油価格が急騰。石油資源を中東からの輸入に依存していた日本の経済は大打撃を受けた。もちろん自動車メーカーにも一大事だったが、当時の私は経営に責任のない立場。大変だったのは、前年5月に独立した富士通ファナック(現・ファナック)を切り盛りしていた父である。
誰にでもピンチや困難な状況、思い通りに行かない時はあり、それをどう対応し、どう対策していくかが大切と思いました。
お客様に対して、希望や理想通りにいかない時、何を優先するか、最大限叶える方法は何かを考え提案致します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月15日(土)
問8
Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 本件契約の目的物たる建物に重大な契約不適合があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。
- 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
- Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。
解説
- “本件契約の目的物たる建物に重大な契約不適合があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、AはBに対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。”正しい。建物に重大な契約不適合があり、建て替えざるを得ないときは、建替えに要する費用相当額の損害賠償請求を行うことが可能です(最判平14.9.24)。
- “本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。”[誤り]。請負契約の担保責任期間には売買契約の規定が準用されます。担保責任を負う期間は当事者同士の合意によって伸長できますが、担保責任の損害賠償権には消滅時効が適用されるので、一般債権の客観的消滅時効期間である10年を超える担保責任期間を定めることはできません(最判平13.11.27民法166条1項)。
新築住宅建築の請負ならば、住宅品確法の定めにより特例で20年まで伸長可能(最低は10年)ですが、本肢は「事務所の用」ですので20年とすることはできません。 - “本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。”正しい。債務の履行が不能になった場合、債権者は債務の履行を請求することできなくなるため、債務者Bは残債務を免れます(民法412条の2第1項)。一方、帰責事由のあるAは請負代金の支払いを拒むことはできません(民法536条2項最判昭51.2.22)。
- “Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。”正しい。請負人が仕事を完成しない間、注文者はいつでも損害を賠償して本件契約を解除することができます(民法641条)。
したがって誤っている記述は[2]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(13)
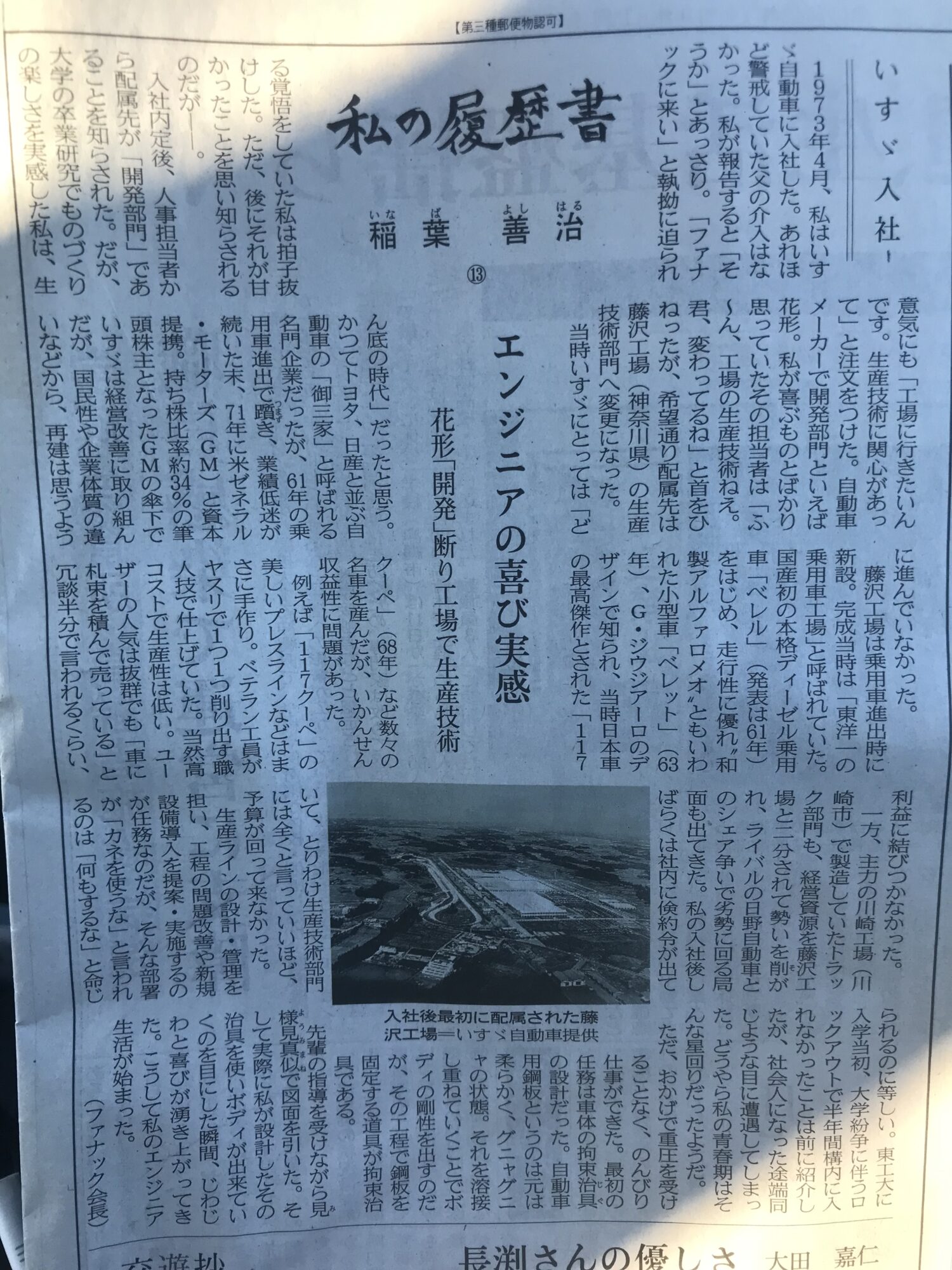
いすゞ入社
エンジニアの喜び実感 花形「開発」断り工場で生産技術
1973年4月、私はいすゞ自動車に入社した。あれほど警戒していた父の介入はなかった。私が報告すると「そうか」とあっさり。「ファナックに来い」と執拗に迫られる覚悟をしていた私は拍子抜けした。ただ、後にそれが甘かったことを思い知らされるのだが――。
入社内定後、人事担当者から配属先が「開発部門」であることを知らされた。だが、大学の卒業研究でものづくりの楽しさを実感した私は、生意気にも「工場に行きたいんです。
自身が力を注ぎ成果に繋がった時、それが実感できる仕事の魅力は強いと思いました。
お客様に対して喜んでいただける提案ができたり、悩みを解決できた時、それを実感させていただいたことに感謝して仕事をしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月14日(金)
住宅比較の吉田です。
問7
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。
- Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
- Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。
解説
- “Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。”[誤り]。受領権者以外の者にした弁済でも、債権者がその弁済により利益を受けた限度において有効となります(民法479条)。
本肢は、Cが債権者であるAに代金を引き渡しているので、Bに過失があったとしてもAが受領した額を限度としてBの弁済は有効となります。 - “Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。”正しい。Dは「受領権者としての外観を有するもの」に該当します。受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が善意無過失のときに限り有効となります(民法478条)。
Bは善意無過失ですからDに対する弁済は有効となり、代金支払債務は消滅します。 - “Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。”正しい。Eは「受領権者としての外観を有するもの」に該当します。受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が善意無過失のときに限り有効となります(民法478条)。
Bは善意無過失ですからEに対する弁済は有効となり、代金支払債務は消滅します。 - “Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。”正しい。売買契約は双務契約であり、双務契約の債務は同時履行の関係にあります。よって、Bは同時履行の抗弁権を主張してAへの代金支払いを拒むことができます(民法533条)。
したがって誤っている記述は[1]です。