スタッフブログ
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(29)

失敗を糧に
理念は「透明」 世襲考えず 対話重視、閉鎖的イメージ刷新
父・清右衛門が亡くなったのは2020年10月。95歳の大往生だった。合議制移行に伴い経営から距離を置いていたこともあり、今では直接父と接した従業員も数少ない。会社は大きく変わった。
かつて父は、ファナックがなぜ必要なこと以外開示しないのかを問われると「自分が経営談義をすると自慢話と思われるからだ」と説明していた。そんな創業者の印象が強烈で、閉鎖的な組織という批判を浴びがちだったのだが、この数年でかなりイメージを変えられたことだろう。
失敗を糧に
失敗や問題を発生させてしまったら、すぐに対策、対応を考え次に活かすことを考える。何度も同じ失敗をしないために何をどう改善するのかが大切と知りました。
同じ失敗することは反省、改善、対策ができていないからです、失敗が起きない対策を考え、実践します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月31日(月)
問6
不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
- 土地の賃借人として当該土地上にある登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
- 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
- 共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
解説
- “不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。”[誤り]。本肢では、AからB、BからC、CからDへと所有者が移っていますが、当事者間であれば登記がなくても所有権を主張することができます。判例では、転々譲渡がされたとき、前々主(B)は民法177条の第三者に当たらないことが示されています(最判昭39.2.13)。同じ理屈で3つ前の所有者に当たるAも対抗関係にある第三者には該当しません。
- “土地の賃借人として当該土地上にある登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。”正しい。土地の賃借人と土地の新所有者は、どちらも土地の使用につき正当な権限を有するので対抗問題となります。土地の賃借人としてその借地上に登記ある建物を所有する者は、その土地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者です(最判昭49.3.19)。新所有者は所有権の移転登記を備えなければ、借地権者に対して賃料を請求したり、債務不履行による解除をしたりすることができません。
- “第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。”正しい。当該第三者は時効の完成前に登場しています。時効取得者は時効完成前の第三者に対して、登記なくして所有権を主張することが可能です(最判昭41.11.22)。

- “共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。”正しい。第三者に所有権を譲渡した相続人は、他の共同相続人の持分の譲渡に関しては無権利者となります。よって、他の共同相続人は、自己の持分のうち法定相続分までは登記なくとも第三取得者に対抗することができます(最判昭38.2.22民法899条の2第1項)。
したがって誤っている記述は[1]です。
宅建勉強1月30日(日)
問4
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和4年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
- 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
- Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。
- 目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
解説
- “BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。”誤り。買主から売主に手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約解除することができます(民法557条)。売主Aが目的物を引き渡す前であっても、買主Bが契約の履行に着手(代金の一部または全部の支払いなど)した場合、もはや手付解除はできないので本肢は誤りです。
- “売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。”誤り。買戻しとは、売買代金や契約の費用を売主に返すことで、売買契約を解除し、売買目的物を取り戻すことができる旨の特約です。買戻しできる期間の上限は10年で、期間を定めなかったときは5年間となります(民法508条3項)。期間の合意がない場合でも買戻しの特約は有効なので、特約自体が無効となるとする本肢は誤りです。
- “Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害を賠償せずに売買契約を解除することができる。”誤り。他人の権利を売買目的物としたときは、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。これは他人物売買であることについて売主の善意・悪意を問いません。もし売主がこの義務を果たさなかった場合には、買主に対する債務不履行となるので、債務不履行の一般原則に従って、買主は売主に対して損害賠償請求をすることができます(民法564条、民法415条)。
- “目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。”[正しい]。種類・品質の契約不適合について買主が売主の担保責任を追及するには、原則として、買主が不適合を知ってから1年以内にその旨を売主に通知する必要があります。ただし、本肢のように、売主が引渡しの時に種類・品質の契約不適合について悪意または善意重過失の場合には、買主は当該通知をしなくても、担保責任の請求権が消滅時効(請求できることを知ってから5年 or 引渡しから10年の早い方)にかかるまで担保責任を追及することができます(民法566条)。
したがって正しい記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(28)

家族
仕事一筋、育児は妻任せ 父が長男の入社お膳立て
本稿も残り2回。家族のことにも触れておきたい。
妻の律子は旧姓・石川。生まれは長崎県鹿町町(現・佐世保市)で小1から高3まで福岡県柳川市に在住。父親が八幡製鉄(現・日本製鉄)系の鉱山会社に勤めていた関係から九州で長く暮らした。東京女子大を出て中学校の国語教師をしていた時、双方の親戚にあたる世話好きの母の従妹の紹介で知り合った。
さまざまなきっかけで誰かと出会い、結ばれ、家族になる。家族の考え方は人それぞれ、大切なことに変わりはない。
家族とのさまざまな経験や考えが自分を家族をどう進む道を作ってきたか、考えました。
お客様に、お客様の家族に良い検討をいただけるように提案していきます。
本稿も残り2回。家族のことにも触れておきたい。
妻の律子は旧姓・石川。生まれは長崎県鹿町町(現・佐世保市)で小1から高3まで福岡県柳川市に在住。父親が八幡製鉄(現・日本製鉄)系の鉱山会社に勤めていた関係から九州で長く暮らした。東京女子大を出て中学校の国語教師をしていた時、双方の親戚にあたる世話好きの母の従妹の紹介で知り合った。
宅建勉強1月29日(土)
問3
成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
- 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
- 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
- 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
解説
成年後見人が成年被後見人を代理して行う対外的な事務には、成年被後見人を保護するため一定の制限が課せられています。
- 居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。
- 成年後見人と成年被後見人の利益が相反する場合には、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法860条)。
- “成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却”不適切。売却の目的物が、居住用建物やその敷地でないため許可は不要です。
- “成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定”[適切]。成年後見人が家庭裁判所の許可を受けなければできない法律行為は、被後見人の居住用の建物やその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定等をするときです。居住用建物に抵当権を設定する本肢は、家庭裁判所の許可が必要となる行為に当たります。
- “成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定”不適切。オフィスビルは居住用建物ではないので、許可は不要です。
- “成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除”不適切。倉庫は居住用建物ではないので、許可は不要です。
したがって適切な記述は[2]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(27)
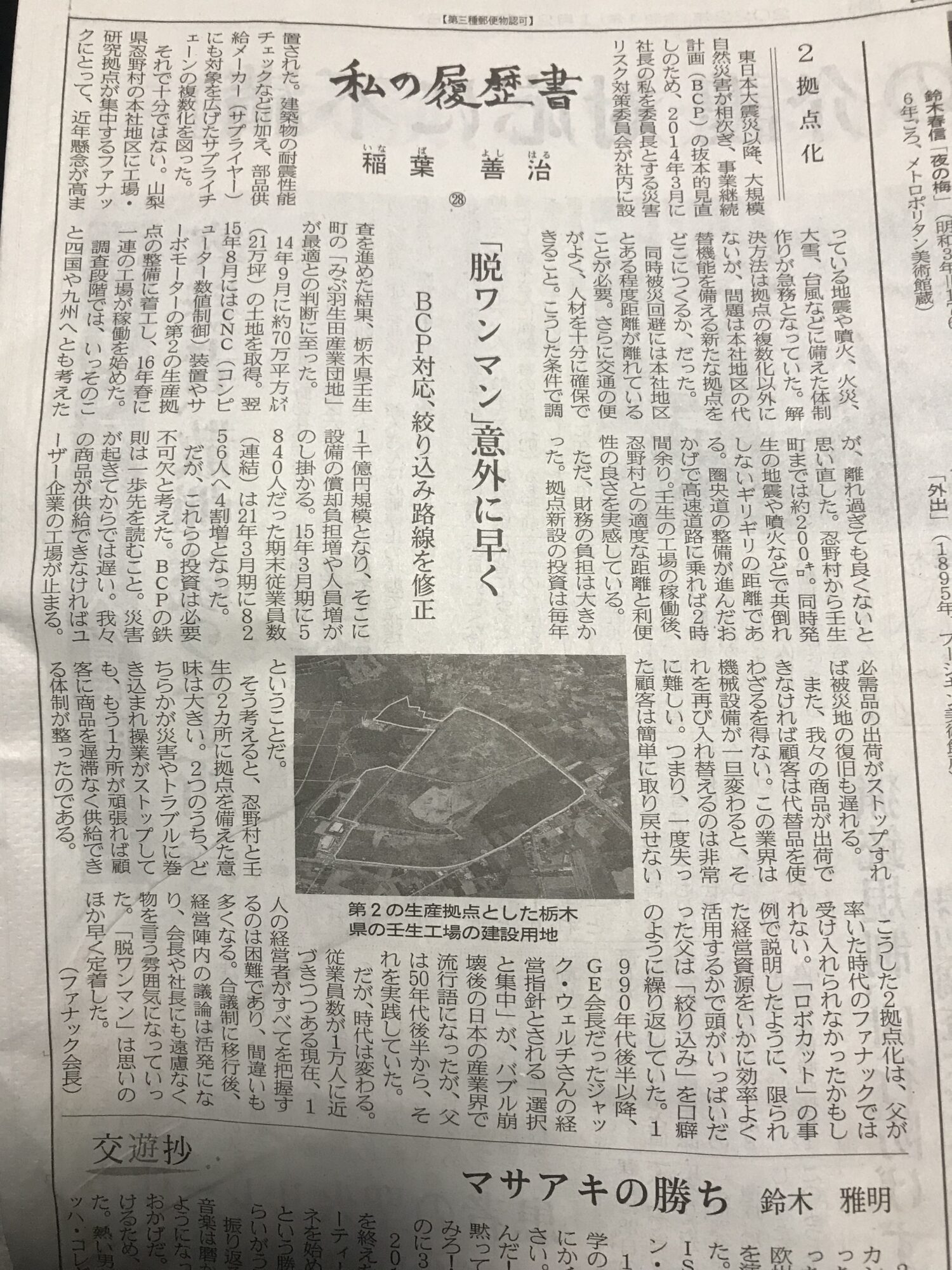
2拠点化
「脱ワンマン」意外に早く BCP対応、絞り込み路線を修正
東日本大震災以降、大規模自然災害が相次ぎ、事業継続計画(BCP)の抜本的見直しのため、2014年3月に社長の私を委員長とする災害リスク対策委員会が社内に設置された。建築物の耐震性能チェックなどに加え、部品供給メーカー(サプライヤー)にも対象を広げたサプライチェーンの複数化を図った。
災害、天災、何かが起こった時の対応策を考えて備えておくことが大切だと知りました。
拠点を準備したり、仕組みを考えて置き、顧客を失わないようにすることが大切だと知りました。
お客様にリスクはあるかを考え提案します。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強1月28日(金)
問2
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
- 隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
- 土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
解説
- “土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。”正しい。境界標とは、点、矢印、十字、T字で、現地上の境界の点や線の位置を示すための標識です。
 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。別段の定めのない限り、境界標の設置・保存費用は両者等しい割合で負担し、測量の費用は土地の面積に応じて負担することになっています(民法223条)。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます(民法223条)。別段の定めのない限り、境界標の設置・保存費用は両者等しい割合で負担し、測量の費用は土地の面積に応じて負担することになっています(民法223条)。 - “隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。”正しい。土地の境界線上にある境界標、囲障(塀や柵のこと)、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます(民法229条)。元々の所有者がわからなくなっている場合にはこの規定の出番です。
- “高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。”[誤り]。高地の所有者は、①その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、②自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、低地のために最も損害の少ない場所及び方法を選び、低地に水を通過させることができます(民法220条)。本規定は、土地の所有者が、浸水地を乾かし、又は余水を排出することは、当該土地を利用する上で基本的な利益に属することから、高地の所有者にこのような目的による低地での通水を認めたものです。
- “土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。”正しい。隣地に直接に雨水を注ぐ構造の屋根を設けることは禁止されています(民法218条)。このような屋根を設けることは土地所有権の侵害行為に当たるので、隣地所有者は所有権に基づき、妨害排除請求または妨害予防請求をすることができます。具体的には雨樋の設置などを求めることになるでしょう。
したがって誤っている記述は[3]です。
宅建勉強1月27日(木)
問1
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。
- 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
- 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
- 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
- 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
解説
- “権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。”誤り。自力救済(法的手続を経ずに、私力の行使により権利回復を果たすこと)は原則として禁止されています。判決文では「緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で」許されると説明しているので、「事情のいかんにかかわらず許される」とする本肢は誤りです。
- “建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。”誤り。賃貸借契約終了後の建物に残された残置物の所有権は、元賃借人にあります。契約が有効に解除されていても、法的手順を踏まずに残置物を処分することは所有権侵害行為に当たるため、残置物を無断で撤去することは許されません。
- “建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。”誤り。鍵の交換や破壊等により賃借人を建物に入れないようにする措置は自力救済に該当し、特段の事情がない限り、数々の判例で不法行為が成立することが認められています。よって、本肢の行為は許されません。
- “裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。”[正しい]。判決文そのままです。私力の行使による権利回復、すなわち自力救済は原則禁止ですが、やむを得ない特別の事情がある場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に認められる可能性があります。
したがって正しい記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 稲葉善治 を読んで(26)
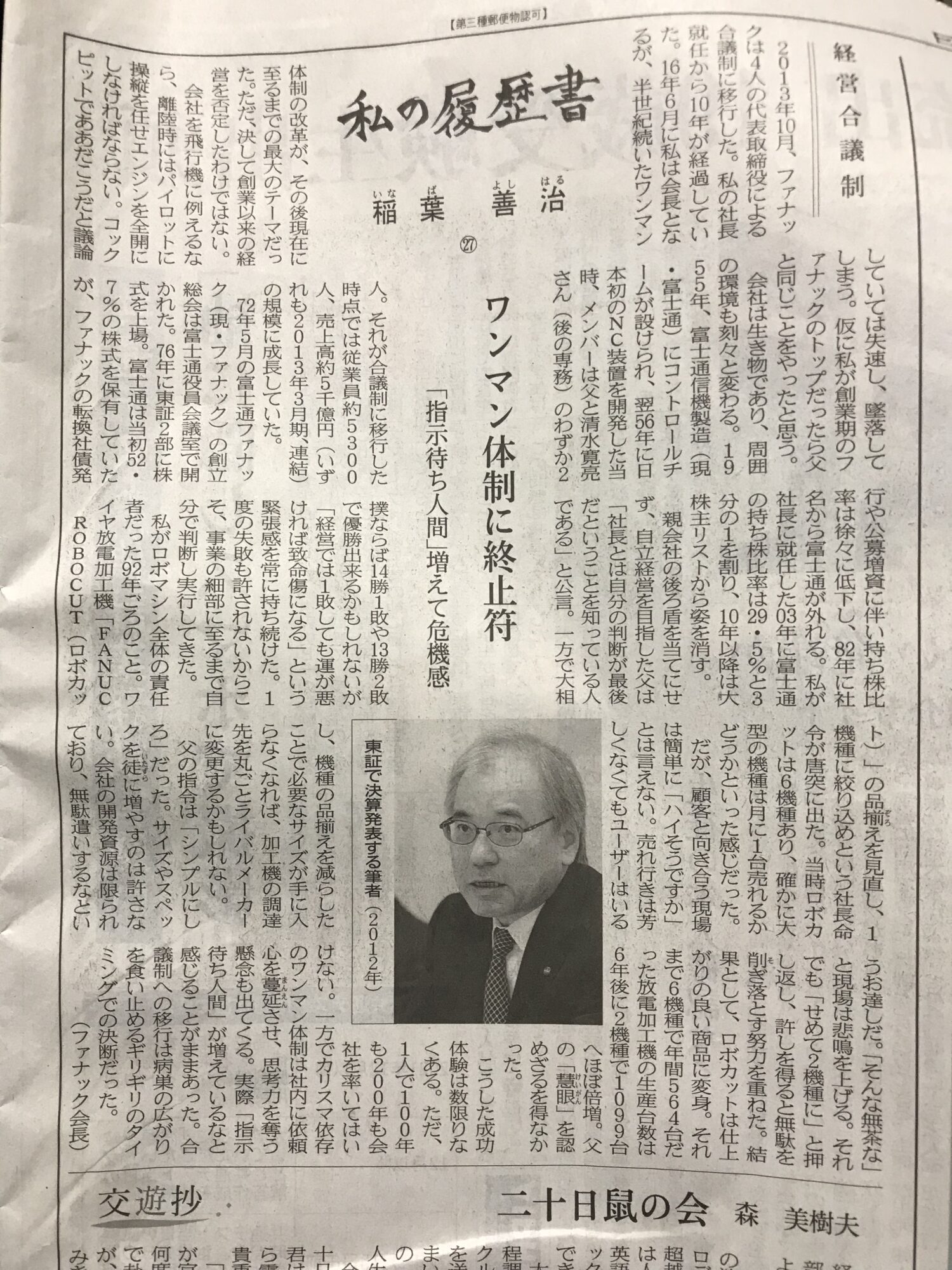
経営合議制
ワンマン体制に終止符 「指示待ち人間」増えて危機感
2013年10月、ファナックは4人の代表取締役による合議制に移行した。私の社長就任から10年が経過していた。16年6月に私は会長となるが、半世紀続いたワンマン体制の改革が、その後現在に至るまでの最大のテーマだった。ただ、決して創業以来の経営を否定したわけではない。
会社を飛行機に例えるなら、離陸時にはパイロットに操縦を任せエンジンを全開にしなければならない。
自分の判断が最後であり、責任を持つこと
さまざまな場面で決断を下さなければならないことがあります。そこで本気で考え、本気で答えるからこそ先に進める。考えなしにその場をやり過ごしてしまうと、のちに大きな問題になって後悔することになります。
簡単に答えは出せない、常にリスクや相手にとってより良い答えはないかと考えるようにします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉