スタッフブログ
宅建勉強2月5日(土)
問8
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
- Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
- Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
- Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
- Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
解説
アとイ、ウとエは同じ事例なので、それぞれの場合を考えます。
【Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合】

代襲相続では、被代襲者の相続分を引き継ぎます。BとCは長男の相続分を引き継ぎ、それを2分の1ずつ分けます。一方、Dは次男の相続分をそのまま引き継ぎます。よって、BとCの法定相続分は各「1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円」、Dの法定相続分は「1億2,000万円×1/2=6,000万円」となります。
したがって正しい記述は「イ」です。
【Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合】

直系尊属が法定相続人となる場合は、父と母を代襲相続するという概念がなく単純に頭数で均等配分されます。よって、E・F・Gの法定相続分は各「1億2,000万円×1/3=4,000万円」となります。
したがって正しい記述は「ウ」です。
以上より正しいものの組み合わせは「イ、ウ」です
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(5)
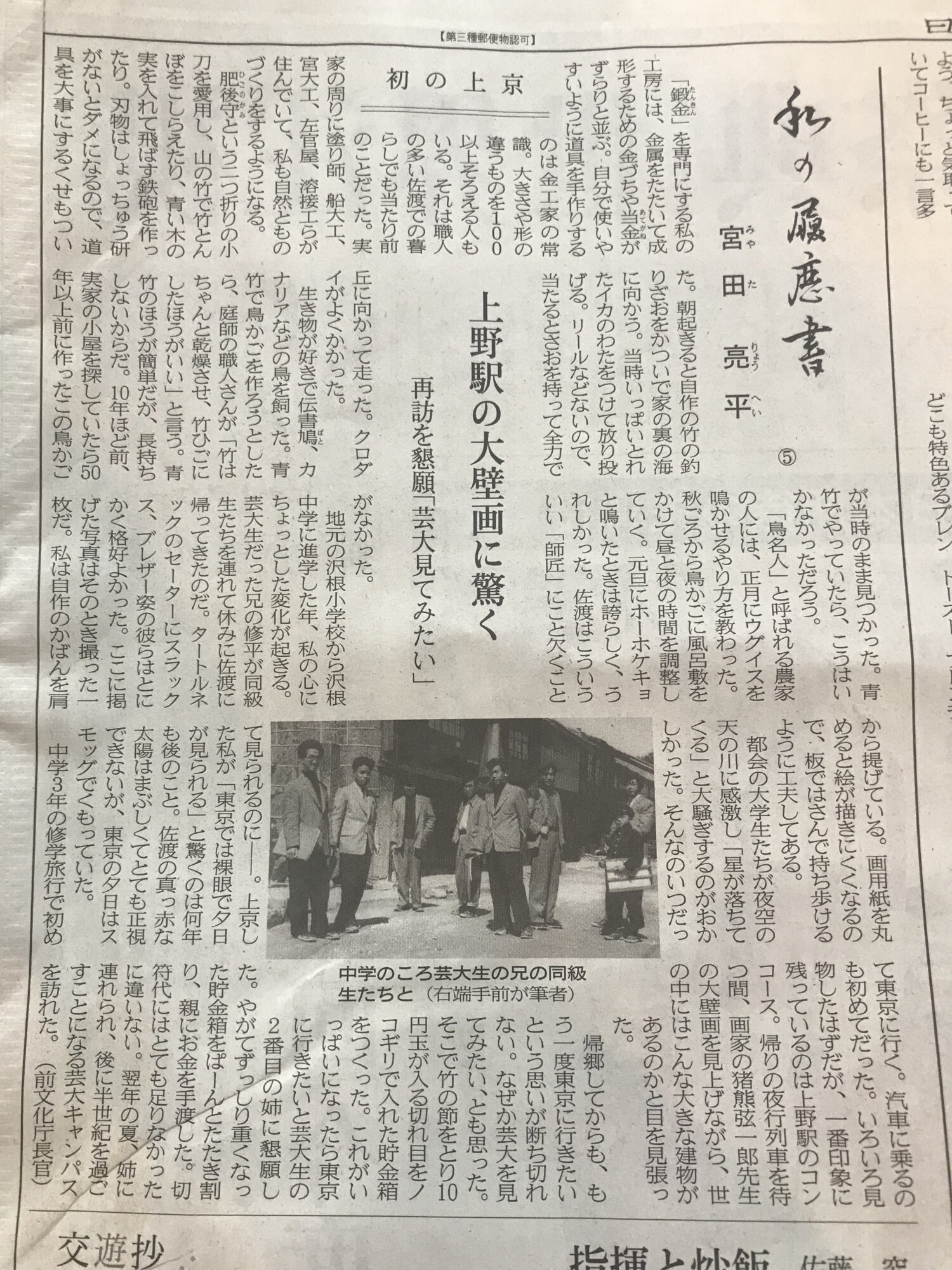
初の上京
上野駅の大壁画に驚く 再訪を懇願「芸大見てみたい」
鍛金(たんきん)」を専門にする私の工房には、金属をたたいて成形するための金づちや当金(あてがね)がずらりと並ぶ。自分で使いやすいように道具を手作りするのは金工家の常識。
大きさや形の違うものを100以上そろえる人もいる。それは職人の多い佐渡での暮らしでも当たり前のことだった。実家の周りに塗り師、船大工、宮大工、左官屋、溶接工らが住んでいて、私も自然とものづくりをするようになる。
道具の研鑽
道具は常に研ぎ、磨きあげなくてはダメになっていく。現状維持は質の低下につながることを学ばせて頂きました。
常に研鑽する習慣をつけている方が職人であり、常に質の高い仕事をしている方がプロです。
何を身につけたいか、何を改善するべきかを考えずに今何をしようとしか考えられておらず、先を見据えて何をしていこう、何をするかが考えられていないことを感じさせて頂きました。
お客様に対して、先を考えての提案ができるように事前のシミュレーション・準備をします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月4日(金)
問7
Aを売主、Bを買主として、令和4年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
- AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
- Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
- 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
解説
- “甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。”誤り。契約不適合責任の追及に関して、買主から売主への通知期間が不適合を知った時から1年に制限されるのは、引き渡された売買目的物が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しないときです。契約不適合責任は、引き渡された目的物が「種類、品質又は数量」に関して契約の内容に適合しないときに追及できますから、本肢のように数量が契約内容に適合しない場合には、通知期間の制限はなく、知った時から5年 or 引渡しから10年の消滅時効にかかるまで請求が可能です(民法562条1項民法566条)。本肢は「2年以内にその旨をAに通知しなければ」としているので誤りです。
- “AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。”[正しい]。契約不適合責任では、売主に対して履行の追完、代金減額、契約解除、損害賠償を請求できます。したがって、売買目的物の引渡しが行われず、それによって損害が生じた場合、買主は売主に対して債務不履行に基づく損害賠償請求ができます(民法564条)。ただし、債務不履行の一般原則に従い、その不履行の責任が売主にないときには損害賠償請求はできません(民法415条)。
- “Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。”誤り。契約等で特段定めのないときに適用される法定利率は、民法改正に伴い5%から3%(3年ごとに1%単位で見直し)になりました(民法404条1項・2項)。本肢は民法改正後に生じた事由ですので、遅延損害金の算定には年3%の利率が適用されます。
- “本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。”誤り。民法改正に伴い、錯誤の効果は無効から取消しに変わりました(民法95条1項)。よって、売主Aは契約の取消しを主張することになります。無効を主張することはできないので、本肢は誤りです。また表意者に重大な過失があるときには原則として取消しを主張することができませんので、その点でも誤りです。
※無効と取消しの違いですが、無効は当初から法律行為の効力が生じていないのに対して、取消しは有効に成立していたものを遡及的に無効にします。また取消しは、取消権者のみが主張できること、期間制限があることが無効と異なります。
したがって正しい記述は[2]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(4)

故郷佐渡
書画・俳句…みなで親しむ 才能ある兄姉との比較につらさ
5歳になった私はある日、両親の前に正座させられた。目の前に白い扇とそろばん。文化と商い、お前はどっちを選ぶかと問われたわけだ。私は扇を手にとり、それから足袋を入れた布袋を下げて姉たちと能の師匠のもとに通うようになった。能舞台が30以上もある佐渡では珍しいことではない。母や姉も扇の使い方やすり足がうまかった。初舞台に立って仕舞を披露したのは小学1年の時だ。
ものがたくさんあるから裕福なのではない。一つのものでも工夫して使い、人のために心を込めて作るから、豊かで清らかなのだ。
何か一つでも相手のために工夫し、相手のために心を込めて行う。日々の行動を相手のために何かをと考えていれば、生活は変えられると感じました。
自分にとってが優先させてしまうと私は楽を選んでしまう、相手にとってを優先すれば考え方・やり方が変わると思います。
お客様にとってどう思われるのか、相手にとってどうなのか考えるようにします。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(3)

蝋型鋳金師
家中に金属の音・におい 父の作業眺めに工房入り浸る
終戦の2カ月ほど前に生まれた私の最初期の記憶の一つは「進駐軍」である。5歳くらいの出来事だった。
1950年に朝鮮戦争が始まると、故郷の新潟県佐渡は様変わりした。ソ連に対する警戒もあって、島で一番高い金北山の頂上に日本海全域を監視するためのレーダー基地が設置された。島に米国の兵隊たちもどっとやってくる。ある日、そのうちの一人が我が家に来た。
安定したものを作ることは退化することだ。
常に現状維持では成長ではなく、実力は下がっていく、新しいことや一つ進んだこと、改善したことに挑戦していくことが成長と知りました。
お客様の問題を一つ一つ改善していきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月2日(水)
問8
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和4年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
- Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
- 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
- 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
1. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。【解説】
以下の条文の通り、Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったときは、本件申込みは効力を失います。
民法526条
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
2. ○ 正しい【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。【解説】
常識的に考えても、申込者が停止条件を付けて申し込んでいるのですから、その条件が成就すれば、記述の本件申込みは効力を失うとなります。
3. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。【解説】
申込みを受けた相手が予想外の損害を被ることがないように、相当な期間は撤回することができません。
民法525条1項
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
4. × 誤り【問題】
AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合
本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(2)

7人兄弟の末子
芸術一家 のびのび育つ 優秀な長兄、若くして日展特選
太平洋戦争末期、1945年のことである。東京美術学校(現・東京芸術大学)の学生だった長兄の宮田宏平が学徒動員された。20歳の兄は6月8日、新潟県佐渡の父と母にあいさつをすませ家を出た。その日の夕方に生まれたのが7人兄弟の末子の私だ。
後に3代目宮田藍堂を継ぐことになる兄は、飛び級で美校に入学するほど優秀だった。2代目の父と同じ、蝋(ろう)型に溶かした金属を流し込む「蝋型鋳金」を得意とした。
自分の役割、責任
家族の中で、組織の中で、自分がいる場でのそれぞれの役割を明確にし、責任を持つことが大切と知りました。
誰かに言われるからではなく、自らこの役割は自分がやると決めやりきることが大切と知りました。
お客様へも良い判断いただけるまでやりきります。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉
宅建勉強2月1日(火)
問7
令和4年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
解説
- “自筆証書遺言によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。”正しい。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものでしたが、2019年1月より財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能になりました。この場合、財産目録の各ページに遺言者が署名押印する必要があります。なお、財産目録とは、自筆証書に添付する相続財産の全部又は一部を記載した別紙のことです(民法968条1項・2項)。
- “公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。”正しい。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。ただし、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するため、以下の人は公正証書遺言を作成する際の証人になることができません(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
- “船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。”正しい。遭難した船舶に乗船中に死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます(民法979条)。その他特別の方式の遺言については以下のものがあります。

- “遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。”[誤り]。遺贈義務者等は、受遺者に対して、相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。催告に対し、受遺者から返答がなかった場合には、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。
したがって誤っている記述は[4]です。
日経新聞 私の履歴書 宮田亮平 を読んで(1)

宮田亮平(前文化庁長官)
- 文化庁長官を務めた宮田亮平さんは、イルカのモチーフで知られる金工作家です。新潟県佐渡で祖父の代からつづく伝統工芸の家に生まれ、東京芸術大学で「鍛金(たんきん)」を学びました。アーティストとして活躍するかたわら、東京芸大の学長を長く務め、文化庁長官として東京五輪・パラリンピックにかかわる文化イベントなどでも尽力しました。その創造性あふれる半生を振り返ります。
美を伝える
「ときめく心」を金工で 芸大学長・文化庁 宮仕え15年
2021年3月末、5年の任期を終えて文化庁長官を退任した。05年からは10年、東京芸術大学の学長を務めた。15年に及んだ宮仕えをなんとか務め上げ、再び本業の金工作家に専念できるようになったところだ。
もっとも、芸大とのかかわりは10年どころではない。1966年に入学、大学院まで在籍して工芸を学び、助手を皮切りに講師、助教授、教授、美術学部長、副学長の役職を次々と仰せつかった。
こころ、感情、ときめき、何を思い何を感じているか。
どう感じているのか、何を思っているのか、本心は。この感情が先のやる気や興味につながったり、反省や改善できるかにつながると感じました。
感受性を豊かにできるようにしていきます。
住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉